筒井康隆の「ロートレック荘事件」(1990年)を20数年ぶりに再読した。
限定された舞台と登場人物の中で連続殺人が起こるいわゆる「Who done it?」(誰が犯人か?)もの。
以前読んだ時にあまりに衝撃的だったので、犯人も含め内容はしっかりと記憶に残っていたが、それでもたいへん面白かった。
この作品は【前人未到の言語トリックで読者に挑戦するメタ・ミステリー】と本の帯にあるように、叙述そのものに仕掛けがあるのだ。
「やられた~!!!」という読後感と共に、作者の「してやったり」という笑みが浮かぶ。
騙される快感を読者に与えられたら作者の勝ちである。
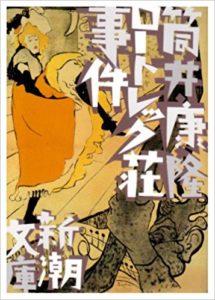
ミステリーには「叙述トリック」というジャンルがあり、古典的なものではアガサ・クリスティーの「アクロイド殺し」(1926年)が有名。
日本では折原一(おりはら・いち)が叙述トリックの名手ではないか。
(私はマニアではないし、「倒錯のロンド」「螺旋館の殺人」しか読んでいないので詳しいことは分からないが、以前出版された週刊文春の「東西ミステリー・ベスト100」国内編に折原作品は1冊も入っていない。これは納得いかないなぁ・・・・)
数年前、本屋で平積みされていた中町信の「模倣の殺意」もこの系統の先駆的作品。
1973年に出版されているが、40年以上経って再評価されているようだ。
叙述トリックものは二度美味しい。
1回目は騙される快感を味わい、2回目で内容を反芻してまた楽しめる。
さて筒井康隆は実験的な作品をたくさん書いているようなので、この「ロートレック荘事件」もその一つなのかもしれない。
作者はミステリー小説を書こうと意図したのではなく、言語トリックを最も効果的に使うためにミステリーという形式を選択したのではないだろうか。
「残像に口紅を」という作品では、最初の章はあいうえおの五十音を全部使って書き、次の章はどれかの文字を抜いた残りで書いていき、次の章では更に文字を減らして・・・・という挑戦的な試みをしていた。すごい。
ジャンル外の小説家が読み応えのあるミステリーを書いている例は他にもある。
坂口安吾の「不連続殺人事件」(1949年)はコテコテの本格推理小説だし、「熊のプーさん」で有名なA・A・ミルンはのどかな英国田園風景の中で殺人事件が起こる「赤い家の秘密」(1921年)を書いている。

創元推理文庫の1981年47版(1959年初版)
今は絶版になっている。







